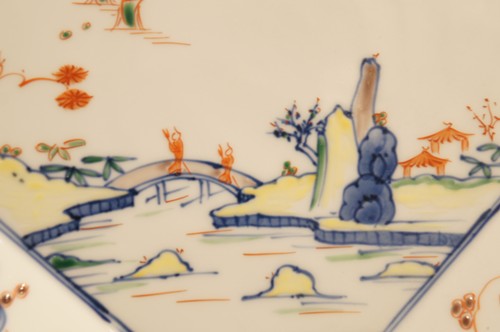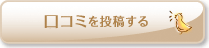食器のみつはた
有田焼「日本の陶磁器の先駆者 〜色絵磁器の美と世界への挑戦〜」デザイン編
江戸初期、日本で初めて磁器が焼かれたといわれる「有田焼」。
前回の〈歴史編〉では、その誕生と発展の歩みをたどりました。今回は、世界へ羽ばたいた“有田焼のデザイン”に焦点を当ててご紹介します。
有田焼のデザインを語るうえで欠かせないのが、透き通るように白く滑らかな“白磁”の存在です。有田の地で採れる良質な陶石が生み出す白磁は、まるで絵画のキャンバスのように、色絵の美しさを引き立てます。
染付(藍色)だけのシンプルな器もあれば、そこに赤・緑・金などの上絵付を施した華やかな色絵磁器もあり、どちらにも有田焼ならではの上品さと緊張感が漂います。
“余白を生かす美”と“装飾の華やかさ”──
この二つの対極を、絶妙なバランスで融合させたのが有田焼のデザインなのです。
時代とともに変化しながらも、有田焼には確かな「様式美」が息づいています。
〈柿右衛門様式〉
柔らかな白磁の上に、赤絵を中心とした色彩で花鳥や草花を描く。
余白の美を生かした構図は、静と動のバランスが絶妙です。
写真:色絵花卉文八角鉢(いろえかきもんはっかくはち)*出典:ColBase
〈古伊万里様式〉
藍・赤・金彩で器の全面を彩り、豪華さを際立たせた様式。
当時は海外でも高く評価され、「IMARI」の名で知られました。
写真左:色絵鶏文平鉢(いろえにわとりもんひらばち)
写真右:色絵花唐草文皿(いろえはなからくさもんさら)*出典:ColBase
〈鍋島様式〉
洗練された構図と上品な配色で、格式と静けさを表現。
落ち着いた品格のあるデザインは、現代でもファンが多い様式です。
写真左:色絵牡丹青海波文皿(いろえぼたんせいかいはもんさら)
写真右:色絵鳳凰文皿(いろえほうおうもんさら)*出典:ColBase
有田焼のデザインには、400年の歴史が刻まれています。
花鳥の文様には四季を愛でる心、金彩の輝きには遠い国への憧れ、そして白磁の静けさには日本人の繊細な感性。器を手に取るとき、そんな背景に思いを馳せてみると、一枚の陶磁器にも深い物語が宿っていることに気づきます。
伝統を大切にしながら、現代の暮らしに寄り添う有田焼。
白磁の清らかさを生かしたシンプルな器や、伝統文様をモダンにアレンジしたシリーズなど、多様なデザインが生まれています。
洋食器とも自然に調和し、どんな食卓にも馴染む——
その柔軟さこそ、有田焼の“デザインの進化”といえるでしょう。
400年の時を経てなお、人々の暮らしを彩り続ける有田焼。
その一枚一枚に宿るデザインの物語が、今日も私たちの食卓をやさしく照らしています。
*出典:「©佐賀県観光連盟」
今回ご紹介する「有田焼」のオススメ商品
錦茶緑金 「松葉前菜皿」(幸楽窯)
縦25 cm× 横11.7 cm× 高さ 2 cm
5,000円(税別・2025年11月25日 現在の価格)
迎春に、お祝いの席に、オススメの前菜皿です。
3品程のお料理を盛り、ワンランク上の食卓に!!
縁起のいい器になっております。
青海波 「急須」(畑萬陶苑)
口径 6.5 cm × 高さ 10.5 cm
20,000円(税別・2025年11月25日 現在の価格)
「青海波」は、穏やかな波がどこまでも続いている様子を表した模様です。
「未来永劫に」「平穏な生活が続くように」という縁起が込められています。
注ぎ口の内側は陶製の茶こしになっており、丸くて高さのある形は、デザイン性だけでなく、茶葉がよく広がるようになっています。
染錦山水 「八角皿」(福泉窯)
直径(辺から辺まで)28 cm× 高さ3.5 cm
20,000円(税別・2025年11月25日 現在の価格)
染付の青い絵付けの上に、赤などで上絵付けをして華やかな仕上がりになっています。
一枚の絵画のようになっているので、飾るのもオススメですが、おもてなしの器として使うのも便利な器です。
食器のみつはた最新情報は、下記のサイトにて発信中です
食器のみつはた
 086-425-5511
086-425-5511
営業時間:午前10時~午後6時
食器のみつはたの最近のニュース
-
 みつはたの「日本焼き物名産地巡り」第8回
みつはたの「日本焼き物名産地巡り」第8回
 3日前
3日前
-
 新年のご挨拶
新年のご挨拶
 3日前
3日前
-
 みつはたの「日本焼き物名産地巡り」第7回
みつはたの「日本焼き物名産地巡り」第7回
 55日前
今見ているニュース
55日前
今見ているニュース
-
 みつはたの「日本焼き物名産地巡り」第6回
みつはたの「日本焼き物名産地巡り」第6回
 123日前
123日前
-
 今年もやってきました!
今年もやってきました!
 132日前
132日前
![donbla. [ドンブラ] - 倉敷の生活&子育て応援情報サイト](/img/common/logo.jpg)