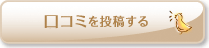食器のみつはた
「清水焼、京の都が育んだ繊細な美
〜京焼・清水焼の優雅な美〜 歴史編」
京焼・清水焼の歴史は、古代から脈々と受け継がれてきた陶磁器の伝統と革新の融合の軌跡です。その起源は明確ではありませんが、平安時代以前から屋根瓦などの焼き物作りが行われ、奈良時代には清閑寺の地に窯が築かれ、土器の製造が行われていました。
「京焼」の名が文献に初めて登場するのは、1605年の神谷宗湛の日記であり、江戸時代初期には粟田口を中心とする東山山麓などで陶窯が築かれ、粟田口焼、八坂焼、清水焼などの名が確認されています。
そして江戸時代初期から東山山麓を中心に広がった焼き物を「京焼」、清水寺に向かう五条坂周辺で作られたものを「清水焼」として呼ばれるようになりました。その後「清水焼」は時代とともに観光地としての発展と生産量の増加によって京焼を代表する存在と認識(京焼=清水焼)されるようになりました。
さらに1977年、京都の焼き物全体を包括する名称として「京焼・清水焼」が伝統的工芸品に指定され、現在の呼称が定着しました。
写真左:「陶器神社」として知られている若宮八幡宮
写真右:若宮八幡宮前にある「清水焼発祥之地 五条坂」記念碑
京焼の発展において特筆すべきは、江戸時代中期に活躍した野々村仁清(にんせい)と尾形乾山(けんざん)の存在です。
仁清は、従来の写しもの中心の茶器製造から、華やかで雅やかな色絵陶器の制作へと京焼の流れを変えました。この技術は多くの窯に影響を与え、京焼の発展を支えました。なかでも江戸初期から中期にかけてつくられた京焼・清水焼は、後に「古清水」と呼ばれています。
一方で、尾形乾山は、京焼の芸術性をさらに押し広げた人物であり、兄である尾形光琳(こうりん)と共に独創的な作品を生み出しました。このように、この時期には仁清と乾山を中心に京焼の黄金期が到来し、その後も多くの陶工がその技法を受け継ぎました。
写真:「色絵月梅図茶壺(いろえげつばいずちゃつぼ)」 野々村仁清作
*出典 ColBase
そして、江戸後期に入ると、京焼は第二の隆盛期を迎えました。奥田頴川(えいせん)が伊万里の技術を取り入れ、京都で本格的な磁器の焼成を始めたことで、新たな発展を遂げます。その後、彼の門下からは青木木米(あおきもくべい)や仁阿弥道八(にんあみどうはち)などの名工が輩出され、彼らの手によって京焼はさらに洗練されたものとなりました。
写真:「色絵飛鳳文隅切膳(いろえひほうもんすみきりぜん)」 奥田頴川作
*出典 ColBase
写真:「色絵桜楓文木瓜形鉢(いろえおうふうもんもっこうがたはち)」 仁阿弥道八作
*出典 ColBase
明治時代になると、京都の陶磁器業界は伝統を守りつつも、西洋の技術を積極的に取り入れ、近代化を図るようになりました。例えば、ウィーン万国博覧会への出品や、ドイツ人技師ワグネルの指導により、新たな釉薬技術が導入され、京焼は一層多様な表現を可能にしました。
シカゴ・コロンブス世界博覧会 出品作
写真左:「色絵金襴手鳳凰文飾壺(いろえきんらんでほうおうもんかざりつぼ)」 七代錦光山宗兵衛作
写真中央:「色絵金襴手花鳥文大瓶(いろえきんらんでかちょうもんたいへい) 九代帯山与兵衛作
写真右:「白磁蝶牡丹浮文大瓶(はくじちょうぼたんうきもんたいへい) 三代清風与平作
*出典 ColBase
こうして京焼・清水焼は、時代ごとの技術革新や名工たちの創意工夫によって発展し続け、現在に至るまで日本の陶磁器文化の中心的存在であり続けています。そして今日も、多くの陶工たちが伝統を受け継ぎながら、新たな意匠を追求し、手仕事の温かみと芸術性を兼ね備えた作品を生み出しています。
<今回ご紹介する「京焼・清水焼」のおすすめ商品>
角鉢(俊山窯)
直径 20.5cm
20,000円(税別・2025年4月25日 現在の価格)
清水焼の優しい雰囲気を残しつつ、1枚あればその場がパッと華やぐような美しさ。
実用はもちろん飾ってもステキな器です。
宝瓶 「三島唐草」(喜信窯)
直径 10cm×高さ7cm 190cc
5,600円(税別・2025年4月25日 現在の価格)
三島手と花唐草にゴールドが入って、とても華やかな雰囲気です。
茶こしの役割をする溝があり、茶こしなしでもご使用いただけます。
組湯呑「枝垂れ桜」(陶葊)
(黒・大) 直径 7.5cm×高さ 9cm
(赤・小) 直径 7.5cm×高さ 8.7cm
30,000円(税別・2025年4月25日現在の価格)
繊細で美しい桜が描かれた、華やかなペア湯呑。
内側はお茶がキレイに見えるようになっています。
持ちやすい形状で、飲みやすいようにフチが少し反っています。
贈り物や記念の品としてもオススメです。
盃「染付着彩祥瑞」(昭阿弥)
直径 8cm×高さ 3.5cm
17,000円(税別・2025年4月25日現在の価格)
小さな盃の中に細かく描かれた吉祥文様がいっぱい。
外は染付のみ、内は華やかになっています。
My盃や贈り物にもオススメ。
職人技の光る盃です。
食器のみつはた最新情報は、下記のサイトにて発信中です
食器のみつはた
 086-425-5511
086-425-5511
営業時間:午前10時~午後6時
食器のみつはたの最近のニュース
-
 みつはたの「日本焼き物名産地巡り」第8回
みつはたの「日本焼き物名産地巡り」第8回
 17日前
17日前
-
 新年のご挨拶
新年のご挨拶
 17日前
17日前
-
 みつはたの「日本焼き物名産地巡り」第7回
みつはたの「日本焼き物名産地巡り」第7回
 69日前
69日前
-
 みつはたの「日本焼き物名産地巡り」第6回
みつはたの「日本焼き物名産地巡り」第6回
 137日前
137日前
-
 今年もやってきました!
今年もやってきました!
 146日前
146日前
![donbla. [ドンブラ] - 倉敷の生活&子育て応援情報サイト](/img/common/logo.jpg)