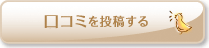やまなかせきざい
山中石材
日本のお盆の行事は、西暦606年で聖徳太子の頃から続いているそうです。インドのサンスクリット語「ウランバナ」を中国語に音写して当てた字です。従って漢字に意味はありませんが、原語のウランバナは「逆さまに吊るされたほど大きな苦痛」を指すそうです。お盆は、御釈迦様の高弟、目蓮尊者に由来しています。亡くなった母親が餓鬼地獄に堕ちて苦しんでいる様子を神通力でみた目蓮尊者は、御釈迦様に「どうすれば母親を救う事が出来ますか?」と尋ねました。その時御釈迦様が「7月15日の夏の修行が終わった日に、大勢のお坊さん達に食べ物を施し、その供養の功績で母親を救ってもらいなさい。」と告げたことが始まりです。
江戸時代に、13日から15日までがお盆となり、迎え火(13日の夜)や送り火(いまは16日)、精霊流しを行い、精霊棚や切子灯籠などを設ける習慣が出来上がりました。
お盆は、お墓におられる御先祖様の精霊を我が家へ迎え、大切にもてなす行事なのです。
山中石材の最近のニュース
-
 【年末年始休業日のお知らせ】
【年末年始休業日のお知らせ】
 50日前
50日前
-
 永代供養をお考えの皆様へ
永代供養をお考えの皆様へ
 190日前
190日前
-
 ✨ちょうちんづくりワークショップのお知らせ✨
✨ちょうちんづくりワークショップのお知らせ✨
 207日前
207日前
-
 3/1(土)から第38回お客様感謝フェアを開催いたし...
3/1(土)から第38回お客様感謝フェアを開催いたし...
 356日前
356日前
-
 改修工事のお知らせ
改修工事のお知らせ
 487日前
487日前
![donbla. [ドンブラ] - 倉敷の生活&子育て応援情報サイト](/img/common/logo.jpg)